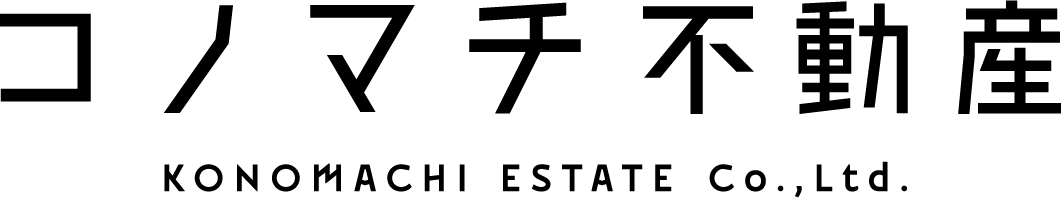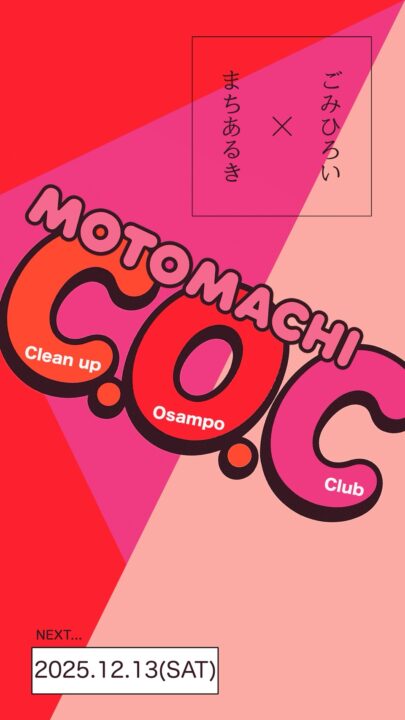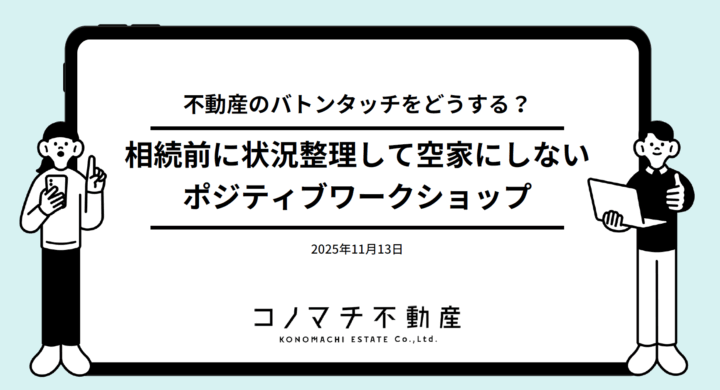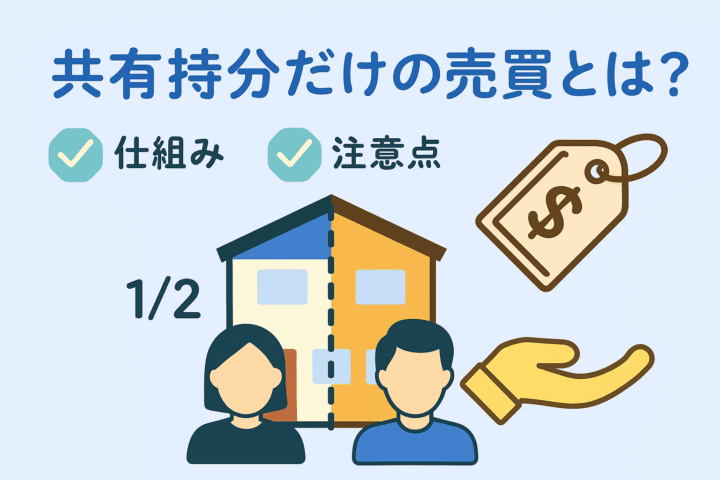民報サロン4ラウンド目。
郡山市社会起業家プログラム「インパクトスタートアップスタジオ」でも発表していました「空き家」について、いつも感じていることや考えていること、私自身この仕事を通しての夢・目標を書かせて頂きました。
本当はこのネタ最後に載せたかったんですが、忙しすぎて間に合わなかったため、先に出してしまったのはここだけの話です。
「空き家を「開き家」へ」
近所を散歩していると庭木がうっそうと伸び「あれ? ここっていつのまにか空き家?」と思ったり、車を運転していて信号待ちにふと家に目をやると、どうにも生気を感じないたたずまいの家があったりする。気になるもんだから遠回りしてもう一度ゆっくり前を通る。そんな怪しい動きをしているのは、おそらく不動産屋だ。私の「空き家かもレーダー」が年々進化しているせいもあるだろうが、ここ10年ほどで「この建物、空き家かも?」と感じるタイミングがすごく増えてきている。
それもそのはず、3~4軒に1軒が空き家になる時代がすぐそこまで来ているのだ。高齢者の寿命や超少子化の流れの中、空き家が爆発的に増えていく試算が出ており、この流れはほぼ運命づけられたようなもので変えるのはなかなか難しい。
空き家問題のニュースや記事などを目にしたことがあると思うが、私たち不動産屋が取引に関わるのは全体の3割程度と言われている。7割の空き家は地域に眠ったままになっている。空き家問題の核心は、この7割の空き家をどう減らしていくかを考える必要があるのだ。ただし、空き家問題は持ち主の気持ちや思い出、親族間の意見の相違などが複雑多岐に絡み、いま困っているわけでもないため、当事者は問題を先送りにしてしまっているのが現状だ。だからこそ、この問題は難しいし、私が情熱を持って取り組む理由がここにある。
更地になり現在は駐車場になってしまったが、昔から地域に根ざした古い建物ほど、気づけばその建物が放つ空気感が、その地域のちょっとした心のよりどころになっていたと感じている。解体するのは話は早いが、一度壊してしまうと同じ建物を再現することは難しい。解体は最終手段として、これからの時代、なるべくごみを出さずに今ある空き家や空き店舗をどう利活用していくかが重要だ。
地域の一員として空き家を面白がって考え、空き家や空き店舗を地域資源のひとつと捉え、その資源を生かすことで何ができるのか―。住むという選択肢だけではなく、店舗利用はもちろん、地域の寄り合いの場でもいいし、共通の趣味の人が集まる場とか、ギャラリーとか、習い事教室としての利用なんてのも面白そうだ。空き家所有者や空き家を使って何かしてみたい人、それぞれがちょとだけ地域に関心を持って一歩踏み出せば少しづつ地域が変わっていく気がする。それこそが、私たちにできるまちづくりだ。
建物には思い出が詰まっている。そして、建てた人の想いもそこには確かにあったはずだ。少し目を閉じて想像してほしい。その想いを引き継いだ人々が空き家だった建物を大切に使い、そこに明かりをともし、にぎやかな声が響いている日常の様子を。空き家だったころに比べ、少なからず家が喜んでいるのではないかと私は感じる。空き家が出るのはしょうがない。ただ、その空き家をできるだけ有効活用し、地域を豊かに変えていくことが私の目標である。
空き家を「ひらくいえ」と書いて「開き家」へ。あなたの思いと建物を循環して、未来へつないでいきたい。私は、いち不動産屋としてそう思うのだ。(郡山市安積町、コノマチ不動産社長)
福島民報 2025年7月2日 朝刊より