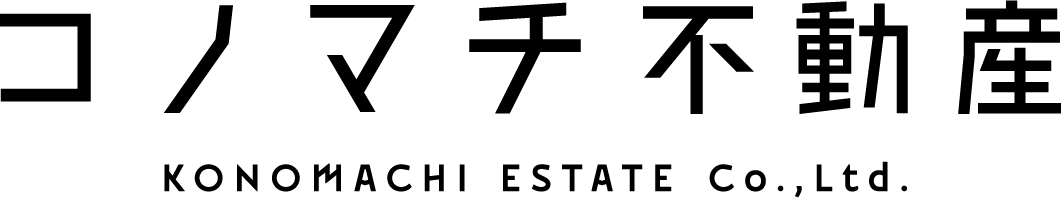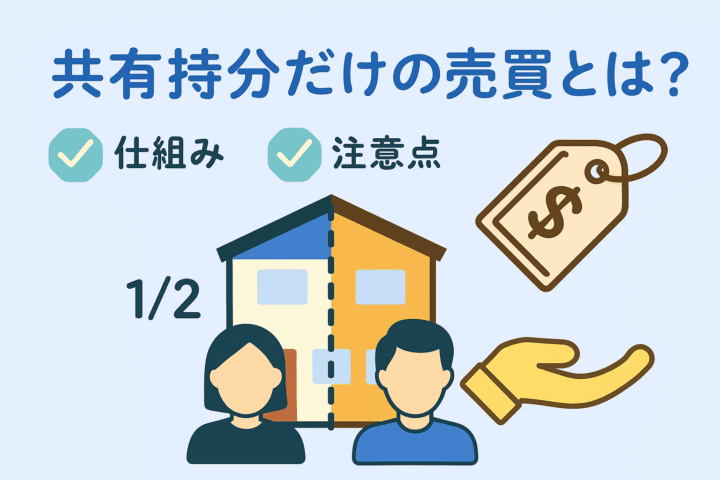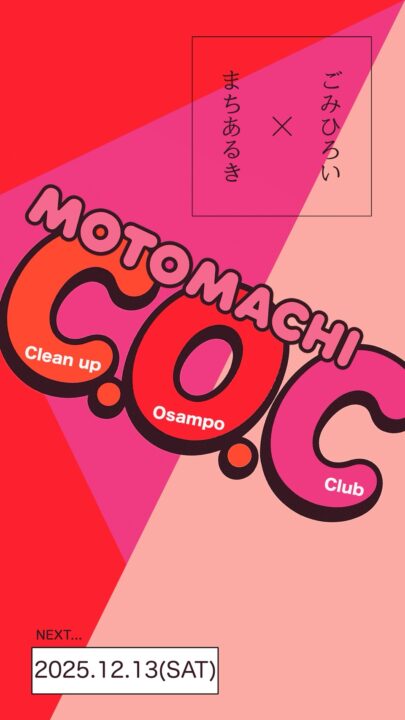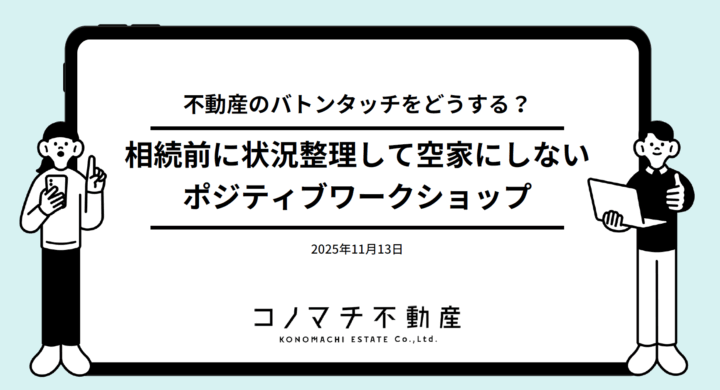1. はじめに
不動産を複数人で所有する「共有持分」は、相続や離婚などをきっかけに発生することが多く、近年その売却ニーズが高まっています。特に「共有持分だけを売却したい」という相談が増えており、一般的な不動産売却とは異なる注意点が存在します。本記事では、共有持分の売却について、仕組み・メリット・デメリット・注意点をわかりやすく解説します。
2. 共有持分とは?
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している場合に、それぞれが持つ所有権の割合のことです。たとえば、兄弟3人で父親の土地を相続した場合、それぞれが1/3ずつの持分を持つことになります。持分は登記簿に記載され、法的にも明確に区分されています。
重要なのは、共有持分は「不動産の一部」ではなく「権利の割合」であるという点です。つまり、物理的に土地の一部を所有しているわけではなく、全体に対する権利の一部を持っているということになります。
3. 共有持分だけを売却することは可能?
結論から言えば、共有持分だけの売却は可能です。民法第206条により、共有者は自分の持分について自由に処分する権利を持っています。そのため、他の共有者の同意を得ることなく、自分の持分だけを第三者に売却することができます。
ただし、物件全体を売却する場合は、民法第251条により共有者全員の合意が必要です。共有持分だけの売却は、あくまで「権利の一部の売却」であることを理解しておきましょう。
4. 売却価格はどう決まる?
共有持分の売却価格は、通常の不動産売却よりも安くなる傾向があります。理由は以下の通りです:
- 買主が物件全体を自由に使えない
- 他の共有者との関係性が不明確
- 利用価値が限定される
そのため、共有持分の買取を専門とする不動産会社に売却するケースが多く、一般の個人が購入することは稀です。査定時には、物件の立地や持分割合、他の共有者の状況などが考慮されます。
5. 売却のメリット・デメリット
メリット
- 💰 現金化できる:使っていない不動産を資産として活用できる
- 🧘♂️ トラブル回避:相続や離婚後の共有関係から解放される
- 📉 固定資産税の負担軽減:持分を手放すことで税負担がなくなる
デメリット
- ⚠️ 他の共有者との関係悪化:第三者が共有者になることでトラブルの原因になることも
- 🧩 利用価値が限定される:買主が自由に使えないため、売却価格が下がる
- 🧾 税務リスク:あまりに安い価格で売却すると、税務署から贈与とみなされる可能性がある
6. 売却の流れと必要書類
売却の流れ
- 不動産会社や専門業者に査定を依頼
- 売却条件の確認(価格・契約内容)
- 売買契約の締結
- 所有権移転登記の手続き
- 売却代金の受け取り
必要書類
- 登記識別情報(登記済権利証)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑登録証明書・実印
- 住民票
- 測量図・境界確認書(土地の場合)
7. よくあるトラブルと対策
トラブル例
- 他の共有者が売却に反対し、関係が悪化する
- 買主が他の共有者と揉めることで、訴訟に発展する
- 過去に支払った固定資産税などの立替金を請求される
対策
- 売却前に他の共有者に通知・説明しておく
- 不動産会社や弁護士に相談する
- 契約書にトラブル回避の条項を盛り込む
8. まとめ
共有持分だけの売却は法的に可能であり、資産整理やトラブル回避の手段として有効です。ただし、価格が安くなる傾向があることや、他の共有者との関係性、税務上のリスクなどを十分に理解したうえで慎重に進める必要があります。
不安がある場合は、共有持分の買取を専門とする業者や、法律の専門家に相談することで、より安全かつ有利な売却が可能になります。
是非、弊社にもお気軽にご相談ください。